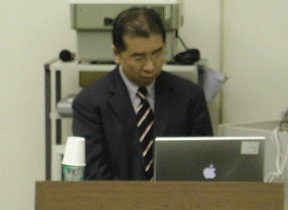丂妛弍僼儘儞僥傿傾悇恑帠嬈僉僢僋僆僼僔儞億僕僂儉偼擔杮醬捝妛夛偲擔杮儁僀儞僋儕僯僢僋妛夛偵嫤巀偄偨偩偒丄
暯惉18擭8寧25擔乮嬥乯屵屻2帪乣5帪偵戧堜僉儍儞僷僗撿娰椪彴島摪偱奐嵜偝傟傑偟偨丅偼偠傔偵丄擔抲鉋巑榊妛挿偐傜娭惣堛壢戝妛偵偍偗傞妛弍僼儘儞僥傿傾
悇恑帠嬈偵偮偄偰丄儔僌價乕儃乕儖偵偨偲偊側偑傜偙傟傑偱偺宱堒偲揥朷偵偮偄偰丄偮偄偱埳摗惤擇僙儞僞乕挿偐傜丄杮妛弍僼儘儞僥傿傾悇恑帠嬈偑傔偞偡傕偺
偲偄偆昗戣偱丄暯惉13擭乣17擭偺妛弍僼儘儞僥傿傾悇恑帠嬈乽嵞惗堛妛擄昦帯椕僙儞僞乕乿偺宲懕丒敪揥偝偣傞偙偲丄戧堜僉儍儞僷僗偵嫆揰傪偍偒丄
僽儗僀儞儊僨傿僇儖僙儞僞乕 (BMC)偲楢実偟偰僩儔儞僗儗乕僔儑僫儖尋媶傪悇恑偡傞偙偲偲杮帠嬈偺傔偞偡揰傪嫮挷偝傟偨屻丄嵟嬤偺枬惈醬捝偺婎慴尋媶偺
恑曕偵偮偄偰榖偝傟傑偟偨丅偮偄偱丄儁僀儞僋儕僯僢僋偺戞1恖幰偱偁傜傟傞媨嶈搶梞弴揤摪戝妛柤梍嫵庼丄恄宱場惈醬捝姵幰偺寖捝傪恖岺恄宱傪梡偄偨恄宱嵞惗偱帯偡偙偲偵悽奅偱弶傔偰惉岟
偝傟偨堫揷桳巎昦堾挿丄暯惉18擭搙偺暥壔岟楯幰偱恄宱壢妛偺戞1恖幰偱偁傜傟傞拞惣廳拤嫗搒戝妛柤梍嫵庼偵傛傝弴師僾儘僌儔儉偵廬偭偰島墘偑峴傢傟傑偟偨丅
奺墘幰偺挿擭偺朙晉側偛宱尡偲幚愌偐傜偵偠傒弌偨丄戝曄暘偐傝傗偡偔丄憿寃偺怺偄偛島墘偱丄奺墘幰偐傜偺乽妛弍僼儘儞僥傿傾悇恑帠嬈僉僢僋僆僼僔儞億僕僂儉乿
偵懳偡傞擬偄儊僢僙乕僕偵枺椆偝傟丄夛応偼擬婥偵偁傆傟偰偄傑偟偨丅恄宱宯擄帯惈幘姵偺侾偮恄宱場惈醬捝傪僥乕儅偲偟偰丄媨嶈愭惗偺椪彴尰応偵偍偗傞
儁僀儞僋儕僯僢僋偺尰忬偲儁僀儞僙儞僞乕偁傝曽丄堫揷愭惗偺恄宱嵞惗偵傛傞恄宱場惈醬捝偺嵟怴偺帯椕曽朄丄擼壢妛偺婡擻暘巕偐傜僔僗僥儉傊偺婎慴尋媶偺揥奐偑椪彴偺栤戣偺夝寛傊偺偝傜側傞
揥奐偲偄偆奺墘幰偺偍榖偑堦杮偺巺偲側傝丄傑偝偵杮帠嬈偑傔偞偡廋暅嵞惗堛妛傪梡偄偨僩儔儞僗儗乕僔儑僫儖尋媶偺曽岦惈傪柧帵偟偰偄偨偩偄偨桳堄媊側僔儞億僕僂儉偱偟偨丅
杮僔儞億僕僂儉偺僾儘僌儔儉偲奺墘幰偺偛島墘撪梕傪埲壓偵娙扨偵傑偲傔偰偄傑偡丅
乗丂僾丂儘丂僌丂儔丂儉丂乗
仜僾儘僌儔儉
擔丂帪 丗 暯惉侾俉擭俉寧俀俆擔乮嬥乯丂14丗00乣 17丗00
応丂強 丗 娭惣堛壢戝妛撿娰椪彴島摪
14丗00乣14丗10
丂丂擔抲丂峢巑榊丂娭惣堛壢戝妛妛挿
丂丂丂丂乽妛弍僼儘儞僥傿傾悇恑帠嬈奐巒偵偁偨偭偰
丂丂丂丂亅僽儗僀儞儊僨傿僇儖僙儞僞乕偲僽儗僀儞儊僨傿僇儖儕僒乕僠僙儞僞乕偺梈崌亅乿
14丗10乣14丗30
丂丂埳摗丂惤擇丂尋媶戙昞幰
丂丂丂丂乽杮妛弍僼儘儞僥傿傾悇恑帠嬈偑傔偞偡傕偺乿
14丗30乣15丗10
丂丂媨嶈丂搶梞丂弴揤摪戝妛柤梍嫵庼
丂丂丂丂乽擔杮偵偍偗傞Multidisciplinary Pain Clinic偺尰忬偲儁僀儞僙儞僞乕偺偁傝曽乿
15丗10乣15丗50
丂丂堫揷丂桳巎丂堫揷昦堾堾挿丒娭惣堛壢戝妛旕忢嬑島巘
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂杮妛弍僼儘儞僥傿傾悇恑帠嬈嫟摨尋媶幰
丂丂丂丂乽擄帯惈醬捝傊偺嵞惗堛椕偺墳梡乿
媥宔
16丗00乣17丗00
丂丂拞惣丂廳拤丂戝嶃僶僀僆僒僀僄儞僗尋媶強強挿
丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂嫗搒戝妛堛妛尋媶壢柤梍嫵庼
丂丂丂丂乽暘巕擼壢妛偵実傢偭偰亅婡擻暘巕偐傜僔僗僥儉傊亅乿
庡嵜丗娭惣堛壢戝妛僽儗僀儞儊僨傿僇儖儕僒乕僠僙儞僞乕
嫟嵜丗擔杮憻婍惢栻姅幃夛幮
嫤巀丗擔杮醬捝妛夛丒擔杮儁僀儞僋儕僯僢僋妛夛
鷸{偵偍偗傞Multidisciplinary Pain Clinic偺尰忬偲儁僀儞僙儞僞乕偺偁傝曽乿
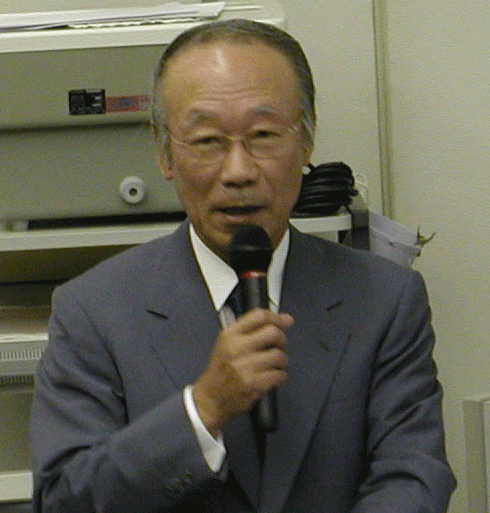 丂
丂
丂尰嵼擔杮偱偼丄捝傒偵懳偟偰揔愗偵帯椕側偝傟偰偄側偄偲姶偠偰偄傞
姵幰悢偑埑搢揑偵懡偔丄変偑崙偱傕昁梫惈偑栤傢傟偰偄傞Multidisciplinary Pain Center乮妛嵺揑捝傒僙儞僞乕)偵偮偄偰丄廬棃傑偱偺Pain clinic丄Pain center 偲斾妑偟偰岅傜傟偨丅
捝傒傪恌丄棟夝偟丄壢妛偡傞偨傔偺Multidisciplinary Pain Center偼丄崙嵺醬捝妛夛偱乽椪彴愱栧壠偲婎慴堛壢妛幰偱慻怐偝傟丄尋媶丄嫵堢丄帯椕傪峴側偆巤愝丅椪彴奺壢偲婎慴堛妛偺暋崌懱偲側傝丄
捝傒偺敪惗婡彉偵婎偯偔恌抐偍傛傃懡妏揑側帯椕傪峴側偆丅慡懱偺攝抲偲偟偰偼丄堛巘丄怱棟妛幰丄娕岇巘丄棟妛椕朄巑丄嶌嬈椕朄巑丄怑嬈憡択堳丄僜乕僔儍儖儚乕僇乕丄偦偺懠堛椕偺愱栧壠偑昁梫偲偝傟傞丅乿偲掕媊偝傟偰偄傞丅
丂枬惈捝姵幰偺乽醬捝乿偼廬棃傑偱偺奣擮偲偼堎側傝乽醬捝峴摦乿乽忣摦斀墳乿乽醬捝乿偲偄偭偨曪妵揑側傕偺偱偁傞偲偟丄奺愱栧暘栰偵傛傞僠乕儉堛椕偑昁梫偱偁傞丅
婍幙揑尨場偺彍嫀偵屌幏偡傞偺偱偼側偔丄醬捝偵婲場偟偨ADL乮擔忢惗妶摦嶌乯偺夵慞傪栚巜偟丄偙傟偙偦偑恀偺堄枴偱偺帯椕丄Multidisciplinary Pain Treatment偵側傞偲擬偭傐偔岅傜傟偨丅
尨場偑柧傜偐偱偼側偄捝傒偱偁偭偰傕偦偺懠偺廋忺場巕偵傕徟揰傪摉偰彍嫀偡傞偙偲偵傛偭偰醬捝娚榓偑壜擻偵側傞偙偲傪帵偝傟偨丅帯椕偵偍偗傞傕偆堦偮偺廳梫側揰偼姵幰偵傛傞擻摦揑側帯椕偵偁傞丅
堛椕幰埶懚揑側帯椕偱偼側偔丄姵幰帺恎偑擻摦揑偵庢傝慻傓偙偲傪懀偡巋寖傪堛椕幰偑梌偊傞僆儁儔儞僩忦審晅偗傪墳梡偟偨帯椕偱偁傞丅偦偟偰帯椕偺嵟廔栚昗偼捝傒偺徚幐偱偼側偔丄QOL(Quality of life)
偺岦忋偱偁傞偙偲傪嫮挷偝傟偨丅偙偺峫偊曽偼変乆堛椕幰丄偁傞偄偼尋媶幰偑僞乕僎僢僩偵偟偰偄傞乽杮幙乿偼壗偱偁傞偺偐傪栤偄捈偡傕偺偱偁傞丅扨偵恄宱場惈醬捝傗怤奞巋寖偺彍嫀偲偄偆偙偲偱偼側偄丅VAS乮Visual analog scale)傗
摦暔儌僨儖偵傛傞斀幩峴摦偱偼昡壙偱偒側偄乽醬捝峴摦乿偑僞乕僎僢僩偱偁傞偙偲傪棟夝偟側偗傟偽側傜側偄丅枬惈醬捝宱楬偵懳偡傞僽儘僢僋偱偼丄擄帯惈醬捝偵懳墳偡傞偙偲傕丄棟夝偡傞偙偲傕偱偒側偄丅
壗傪偡傟偽壗偑帯傞偺偐丄杮摉偵昁梫側偙偲偼壗側偺偐傪徢椺偺徯夘傪娷傔偍榖偵側傜傟偨丅
丂崱屻敪揥偺朷傑傟傞Multidisciplinary Pain Center偱偼丄摦暔儌僨儖傗婛懚偺忣曬偺傒偱偼棟夝偟偒傟側偄徢椺偺乽懡條惈乿偵懳墳偡傞偙偲丄偦偟偰庢傝慻傓奺愱栧暘栰偵傛傞嫟捠偺棟夝偙偦偑廳梫偱偁傞
偙偲傪傑偲傔偺尵梩偲偟偰偛島墘傪廔偊傜傟偨丅乮暥愑 T.K.)
乽擄帯惈醬捝傊偺嵞惗堛椕偺墳梡乿
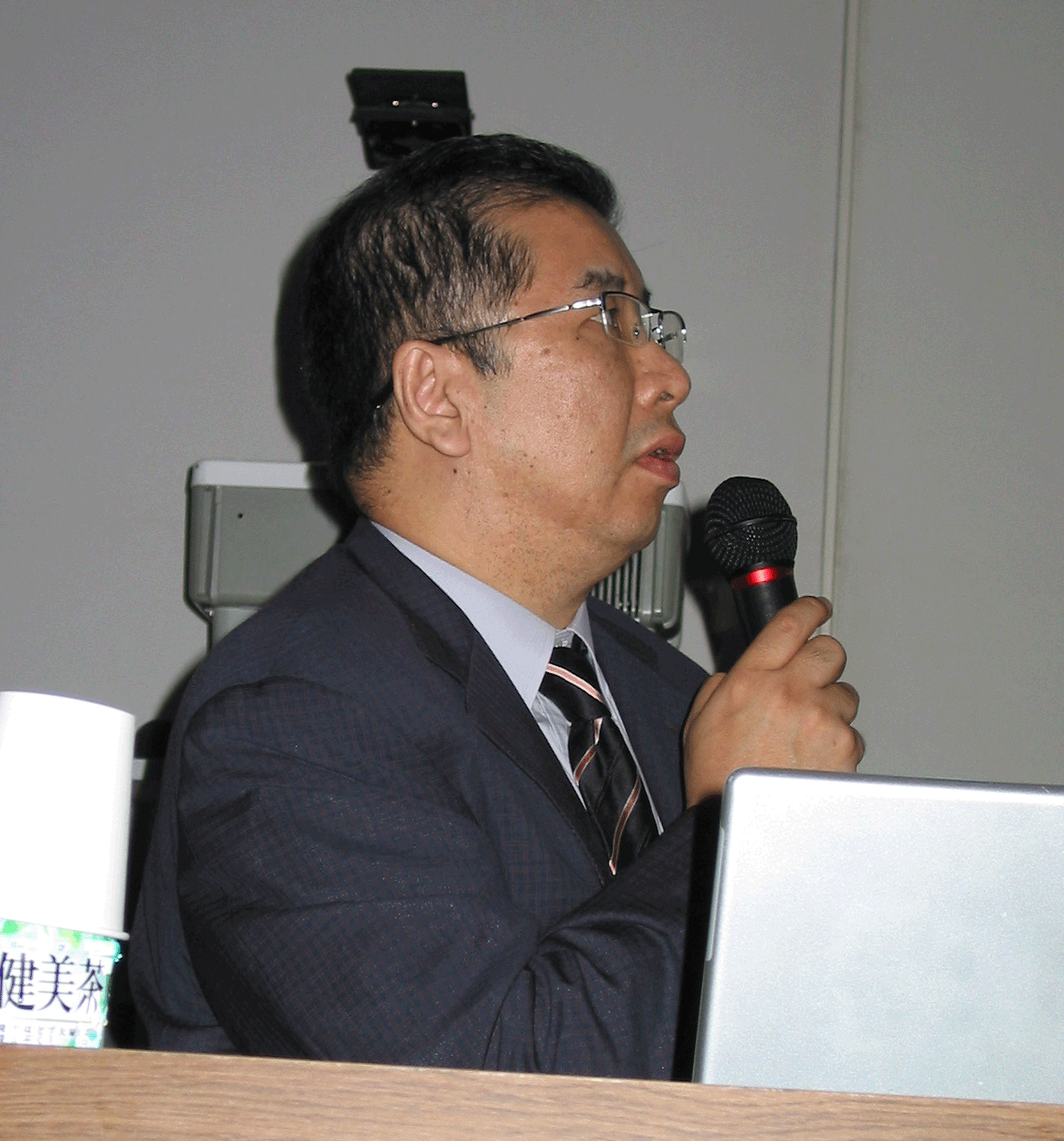 丂
丂
丂傾儘僨傿僯傾丄峉弅丄怳愴側偳拞悤恄宱愢偱愢柧偝傟偰偒偨徢忬偑偁傞
暋崌惈嬊強捝徢岓孮乮Complex regional pain syndrome, CRPS乯偱傕昦懺傪愢柧偱偒傞枛徑恄宱懝彎偺強尒偑偁傝丄偄傑傑偱崻帯偑晄壜擻偲峫偊傜傟
偰偒偨懳徾偱偁傞CRPS type II乮侾杮偺恄宱傗偦偺庡梫側暘巬偺晹暘懝彎屻偵婲偙傞丄捠忢庤傗懌偺椞堟偺庈擬捝丄傾儘僨傿僯傾丄捝妎夁晀乯偵嵞惗
帯椕傪揔梡偟恄宱嵞寶偡傞偙偲偱幮夛暅婣偑偱偒傞傑偱偵帯桙偡傞偲偄偆夋婜揑側奜壢揑側枛徑恄宱帯椕傪曬崘偝傟偨丅崅暘巕億儕儅乕偱偁傞polyglycolic
acid (PGA)娗偵collagen慄堐傪僗億儞僕忬偵媗傔偨傕偺乮PGA-collagen tube, Brain Res. 868: 315, 2000乯傪恖岺恄宱偲偟偰梡偄丄枛徑偺恄宱懝彎晹埵
傪嵞寶偡傞偲偄偆嵟怴偺夋婜揑側帯椕朄乮Neurosurgery 55: 640, 2004, Pain 117: 251, 2005乯偵偮偄偰弎傋傜傟偨丅恖岺恄宱帯椕偺僐儞僙僾僩偼乽応偺棟榑乿偲偄傢傟傞
帺屓廋暅丒嵞惗偱偁傞丅惗懱慻怐偺堐帩丒廋暅丒嵞惗偼偦偺応偺娐嫬偑巟攝偟偰偄傞偺偱惗懱偺帯桙椡偵婜懸偟恄宱傪廋暅丒嵞惗偝偣傞偲偄偆偙偲偱偁傞丅乽懌応乿偲偟偰偺
恖岺恄宱娗偲丄廃曈偐傜恖岺恄宱娗傊恑擖偡傞乽嵶朎乿丄寣峴嵞寶偵傛傞寣塼偵傛傞娐嫬堐帩偲廃曈偐傜偺乽憹怋場巕乿偲偄偆嵞惗帯椕偵昁恵側嶰庬偺恄婍偵
傛傞恄宱嵞寶偵傛傝帯桙偡傞丅庤偺枛徑恄宱偺懝彎晹埵傪PGA-collagen tube偵傛偭偰偮側偘偰18儢寧屻偵嵞惗偝傟偨恄宱偼揹婥巋寖偵傛傝妶摦揹埵偑庝婲
偝傟傞偙偲傪帵偟丄幚嵺偵恄宱嵞惗偑婲偙偭偰偄傞偙偲傪徹柧偝傟偨丅
丂帺壠恄宱堏怉傛傝傕桪傟偰偄傞偺偐丠偲偄偆媈栤偵懳偟偰偼丄將偺帺壠恄宱堏怉偱偼60亾偱恄宱庮偑宍惉偝傟傞偺偵懳偟丄PGA-collagen tube偱恄宱娫傪
偮側偘傞偙偲偵傛傝100%恄宱嵞惗偟偨偙偲偐傜偦偺桳岠惈傪帵偝傟偨乮Brain Res. 1027: 18, 2004乯丅幚嵺丄椪彴偱傕帺壠恄宱堏怉偺惉岟妋棪偼栺40%偱
偁傝丄偙偺寢壥偼椪彴僨乕僞偵崌偭偨傕偺偱偁偭偨丅侾擭埲忋庤巜偺捝傒傪慽偊傞姵幰偺嬊強強尒偲偟偰偼恄宱晄楢懕丄恄宱庮丄擏娽揑恄宱庮側偟丄枛愡崪
傊偺桙拝丄夁嬞挘徢岓孮偲偦偺尨場傪嬫暿偱偒傞偑丄偄偢傟偺応崌偱傕恖岺恄宱偵傛傞枛徑恄宱偺嵞惗帯椕偺揔梡偱帯桙偡傞徢椺偑偁傞丅側偐偱傕丄擏娽揑偵恄宱偺晄楢懕惈傗恄宱庮
偑傒傜傟側偄徢椺偱傕姵晹偺恄宱偼揹婥巋寖偱妶摦揹埵傪庝婲偟側偄偙偲偑偁傝丄偦偺応崌偵偼嵞惗帯椕偑岠壥偺偁傞偙偲傪帵偝傟丄弍拞揹婥巋寖朄偺妋棫偑廳梫偱偁傞偙偲傪帵偝傟偨丅
崱傑偱偵恄宱場惈醬捝丄CRPS偲恌抐丄徯夘偝傟丄惗懱撪嵞惗帯椕傪巤偟偨153椺拞127椺丄偮傑傝83亾偑帯桙偟丄幮夛暅婣傑偱偱偒偨偲嬃堎揑側曬崘傪偝傟偨丅
丂偙傟傜懡悢偺椪彴宱尡偐傜丄恄宱場惈醬捝傗CRPS偵懳偡傞惗懱撪嵞惗帯椕偺椪彴忋偺栤戣揰偲偟偰嘆挿婜娫偺嵞惗帪娫偲晄埨掕側嵞惗帪偺抦妎夁晀傪偳偆
崕暈偡傞偐丄嘇摿堎側椪彴宱夁丄嘊庤弍帪偺條乆側嬊強強尒偵偳偆懳墳偡傞偺偐側偳嵞惗帯椕偵偍偗傞栤戣揰傪楍嫇偝傟偨丅
偝傜偵丄PGA-collagen tube偺恄宱嵞惗偵傛傞CRPS偺嵞惗帯椕偼桳岠偱偁傞偑丄恄宱場惈醬捝偵晅悘偡傞懡嵤偱暋嶨側夝寛偡傞傋偒怴偨側栤戣傪
懡悢僋儘乕僘傾僢僾偝傟丄婎慴偲椪彴偐傜峔惉偝傟傞杮妛僽儗僀儞儊僨傿僇儖儕僒乕僠僙儞僞乕偵偍偗傞廤妛揑傾僾儘乕僠偑昁梫偱偁傞偲掲傔偔偔傜傟偨丅乮暥愑 S.M.乯
乽暘巕擼壢妛偵実傢偭偰亅婡擻暘巕偐傜僔僗僥儉傊亅乿
 丂
丂
丂偙傟偐傜偺擼壢妛偼丄椪彴偲偲傕偵婎慴揑側惉壥傪傕偲偵丄
偝傜側傞堛妛揑側敪揥傪昁梫偲偡傞偺偱丄偙偺妛弍僼儘儞僥傿傾悇恑帠嬈偑丄暥壢徣偵擣傔傜傟偨偙偲偼丄婌偽偟偄偙偲偲朻摢偵弎傋傜傟偨丅
擼壢妛偺婎慴揑尋媶偼丄傑偩擼偺婡擻傑偱棟夝偡傞傑偱偵帄偭偰偄側偄丅僸僩偺堚揱巕慡峔憿偺夝柧偵傛傝栺俀乣俁枩偺堚揱巕偑懚嵼偟丄
懡偔偺婡擻暘巕偑丄屄乆偺婡擻偑撈棫偱偼側偔僔僗僥儉偲偟偰嶌梡偟偰偍傝丄崱屻偺擼尋媶偼丄婡擻暘巕偐傜僔僗僥儉傊偺夝愅偵揥奐偝傟傞偙偲偑
廳梫偩偲弎傋傜傟偨丅婡擻暘巕偺幚懱偺夝柧偐傜偼偠傑傞擼尋媶偺恑揥偲曽岦惈偵偮偄偰尵媦偝傟偨丅
丂惗柦壢妛偺僗僞乕僩偺帪戙丄堚揱巕岺妛偺庤朄傪摫擖偟丄捝傒偺恄宱儁僾僠僪丄僒僽僗僞儞僗P偺慜嬱懱傪柧傜偐偵偝傟丄
峔憿偺帡偨僒僽僗僞儞僗K傕摨掕偝傟偨丅偦傟傜偺儁僾僠僪偺栻棟嶌梡偺嵎堎傛傝丄奺乆偺庴梕懱傊尋媶傪揥奐丄傾僼儕僇僣儊僈僄儖棏曣嵶朎傪梡偄丄
堚揱巕岺妛偲揹婥惗棟妛傪慻傒崌傢偣偨怴偟偄僋儘乕僯儞僌朄傪妋棫偝傟丄庴梕懱偺僋儘乕僯儞僌偵惉岟偝傟偨丅偝傜偵丄恄宱宯偵偍偄偰恄宱嫽暠傪
扴偆僌儖僞儈儞巁庴梕懱傕柧傜偐偵偝傟偨丅椪彴偵懳偟偰婎慴揑側尋媶偵偼丄怴偟偄曽朄傪奐敪偡傞偙偲偵傛偭偰丄怴偨側揥奐傪傕偨傜偡昁梫偑偁傝丄
偦偺偙偲偵傛傝偝傜側傞敪揥偑偁傞偙偲傪嫮挷偝傟偨丅
丂偝傜偵丄栐枌偺拞偱岝偺柧埫偺擣幆偼丄偄偢傟傕僌儖僞儈儞巁偵傛偭偰扴傢傟偰偄傞偑丄
偦偺庴梕懱偱偁傞mGluR6偲AMPA庴梕懱偑堎側傞恄宱嵶朎偵敪尰偡傞偙偲偵傛偭偰岝偺柧埫偺幆暿偺寛掕偟偰偄傞偙偲傪曬崘偝傟偨丅敪昞偐傜10擭屻丄
堚揱惈栭栍徢偺姵幰偺20亾偵偼mGluR6偺堚揱巕堎忢偑敪尒偝傟丄婎慴尋媶偺寢壥偑幘姵偵娭梌偟偰偄傞偙偲偑柧傜偐偲側偭偨丅傑偨丄彫擼偱
塣摦婰壇偵娭梌偡傞恄宱僱僢僩儚乕僋偵偍偄偰丄摿掕偺恄宱嵶朎偐傜偺僌儖僞儈儞巁偺暘斿傪壜媡揑偵慾奞偱偒傞儅僂僗傪嶌惢偟丄忦審晅偗弖栚斀幩偵偍偗傞僌儖僞儈儞巁偺
壜慪揑側嶌梡婡峔傪柧傜偐偵偝傟偨丅暘巕惗暔妛傪梡偄偨暔幙揑婎斦偵壛偊丄恄宱偺揹婥揑斀墳傪揹婥惗棟妛丄恄宱嵶朎偺懡條惈傪宍懺妛丄偝傜偵
屄懱儗儀儖偺擼婡擻偺摦暔峴摦妛側偳傪嬱巊偟側偑傜擼尋媶傪恑傔偰偄偔昁梫惈傪弎傋傜傟偨丅
丂嵟屻偵丄惗懱偺忣曬偼傾僫儘僌揑斀墳偱偁傞偑丄恄宱嵶朎偺嫽暠偲梷惂偲偄偆傛偆側岆傝偺彮側偄夝傝傗偡偄僨僕僞儖揑側斀墳偵張棟偟丄
偦傟傪偆傑偔摑崌偡傞偙偲偵傛傝丄偝傜偵忣曬偺曐帩偲慖戰揑側拪弌偵傛偭偰丄恄宱宯偼崅師婡擻傪敪婗偡傞偙偲傪棟夝偡傞昁梫偑偁傞偲弎傋傜傟偨丅
婎慴偐傜椪彴傊慽偊傞傛偆側丄椪彴偺栤戣傪偲傜偊傞傛偆側尋媶偵敪揥偡傞偙偲傪婜懸偝傟偨丅乮暥愑 E.A.乯